こんにちは、Dextaです。
海外で会社を経営していると、避けて通れないのが「税務調査」です。
日本では公平性や透明性がある程度担保されていますが、東南アジアでは必ずしもそうではありません。
こちらに非がないことを、こちらから証明しなければならない。そんな構図に、何度も違和感を覚えました。
今回は、私自身が体験した税務の理不尽さと、そこから得た教訓を紹介します。
1.親会社子会社構造と「移転価格」の疑い
東南アジアでは、日本や他国の親会社が子会社や製造工場として現地法人を設立するケースが多くあります。
その際、親会社が販売先や仕入れ先になることも珍しくありません。ところが、この関係は税務署にとって「移転価格を疑う格好の材料」になりがちです。
価格が市場と異なると、「利益操作ではないか」と疑われ、調査対象になってしまうのです。
2.監査が入ると高確率で粗探しされる
一旦監査や査察が入ると、細かい粗探しが始まります。本来は違反ではないことや、ちょっとした解釈の相違も「重大な問題」にされがちです。
説明を尽くしても「聞く耳を持たない」ケースもあり、最終的に罰金や追徴課税に持っていくのが常套手段。
すべての担当官がそうとは限りませんが、経営者側から見れば、無罪放免というよりも、被害を最小化するしかないのが現実です。
3.実際に受けた理不尽な追徴課税
弊社でも、得意先から格安で仕入れた原料について「不当に安価だ」と疑われたことがあります。
当局は独自の統計データを根拠に、市場価格より高い金額を基準に課税。正当な取引であっても追徴を課されました。
最終的には裁判に持ち込み、2年以上かけて取り返しましたが、その間に消費した時間と労力(と弁護士費用)は計り知れませんでした。
場合によっては、先にデポジットを支払わされることもあり、資金繰りへの打撃も無視できません。
4.税収事情によって左右される査察強化
さらに厄介なのは、税務署の査察や監査が国の税収事情によって強化される点です。
その年の税収が減っていると、当局は「取りやすいところから取る」という姿勢を強めます。つまり、会社の経営状態が問題だから調査されるとは限らず、国の財政事情に巻き込まれることも多いのです。
こうした不確実性こそ、海外経営の大きなリスクだと痛感しました。
5.理不尽さを前提に備える
東南アジアで経営する以上、税務リスクから完全に逃れることはできません。
移転価格の疑い、不透明な課税基準、国の税収事情に左右される査察——これらは理不尽ですが、現実でもあります。
だからこそ、帳簿を常に整え、専門家と連携し、最悪のシナリオを想定しておくことが何よりの防御策になります。
理不尽さを嘆くだけではなく、それを前提に備えることが、海外で生き残るための必須条件なのです。
▶よろしければ、こちらもあわせてお読みください:
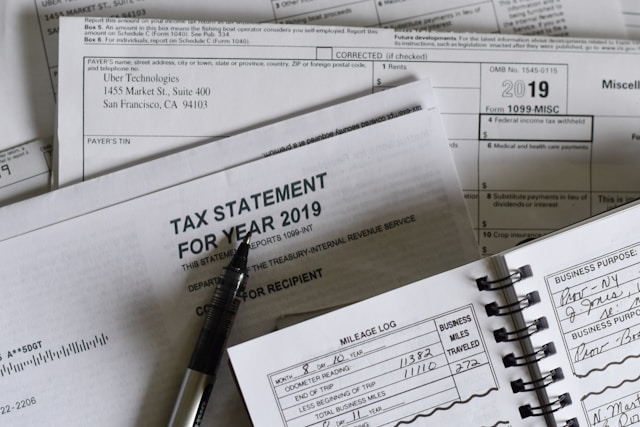


コメント